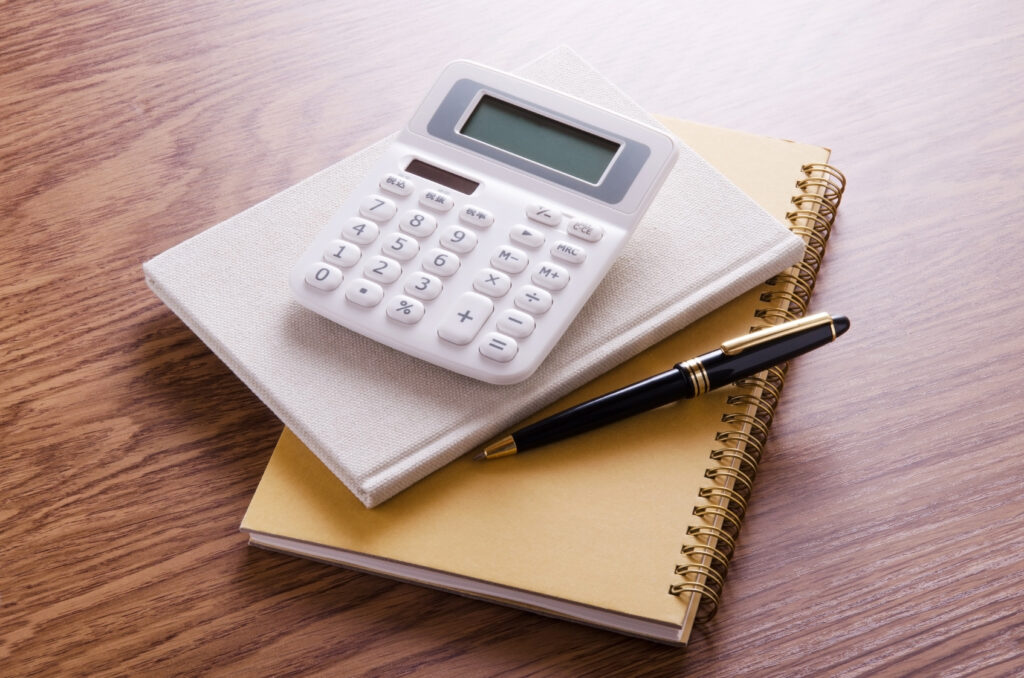
インプラントの費用は保険適用外となることが多いため、経済的な負担は決して軽くありません。
「インプラントって安くならないの?」…そんな時に知っておきたいのが医療費控除です。
実はインプラントは医療費控除の対象になることがほとんどで、税金の還付を受けることで実質的に費用負担が軽減されるのです。
ここでは医療費控除とは何か、対象条件ややり方、注意点について詳しく解説します。
目次
■医療費控除とは?
医療費控除の基本ルール
医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えたときに所得税や住民税の負担を軽減できる制度です。
対象となるのは1月1日から12月31日までの医療費で、10万円(総所得が200万円未満の方は所得の5%)を超えた分が控除の対象となります。
控除額の計算方法
-
年間の医療費の総額-保険金などで補填される金額-10万円
または
-
年間の医療費の総額-保険金などで補填される金額-総所得金額等の5%
例えば、インプラント治療で50万円を支払った場合、保険などの補填がなければ、10万円を差し引いた40万円が控除対象額です。
これに所得税に応じた税率をかけます。
|
所得合計額 (課税される所得額) |
所得税率 |
控除額 (所得から差し引かれる控除額) |
|
195万円未満 |
5% |
0円 |
|
195万円超330万円未満 |
10% |
97,500円 |
|
330万円超695万円未満 |
20% |
427,500円 |
|
695万円超900万円未満 |
23% |
636,000円 |
|
900万円超1,800万円未満 |
33% |
1,536,000円 |
|
1,800万円超4,000万円未満 |
40% |
2,796,000円 |
|
4,000万円超 |
45% |
4,796,000円 |
所得税率が20%の方であれば、およそ8万円の税金が戻る計算になります。
■インプラントは医療費控除の対象になる?
噛む機能を回復する治療は対象
インプラント治療は噛む機能を改善する医療行為とみなされるため、多くが医療費控除の対象となります。
歯を失ったままでは食事や発音に支障が出るため、機能回復を目的としたインプラントはこの対象内となることがほどんどです。
■医療費控除のやり方
領収書を必ず保管する
まずは治療時にもらう領収書を大切に保管しておきましょう。
インプラント治療にかかった金額が明細としてわかることが重要です。
医療費控除の明細書を作成する
国税庁のホームページからダウンロードできる医療費控除の明細書に記入し、支払った金額をまとめます。生計を共にする家族分を合算することも可能です。
確定申告で申請する
医療費控除は会社員の方が行う年末調整では受けることができません。
2月16日から3月15日までの確定申告期間に、税務署またはe-Taxを利用して忘れずに申請しましょう。
■インプラント費用以外でも控除できるもの
通院にかかる交通費
治療のために通院した際の電車やバスの代金は医療費控除の対象となります。
子どもの治療に付き添った場合の交通費も認められることがあります。
関連する治療費
インプラントのために必要となる骨造成や歯周病治療などの付随処置も控除の対象です。
治療に直接関連する費用はまとめて申告しましょう。
対象外の費用
タクシーやマイカーでの通院、ガソリン代や駐車場代は原則対象外です。
ただし、急を要する場合や、電車、バス等の利用ができない場合は医療費控除の対象となることがあります。
■医療費控除を利用する際の注意点
保険金や給付金は差し引かれる
生命保険の給付金や高額療養費制度で補てんされた金額は医療費から差し引かれます。
そのため実際に自己負担した額だけが対象です。
デンタルローンの場合
ローンを利用して分割払いしている場合は、その年に契約した治療費の総額を医療費控除として計上することができます。ご自身は分割で返済していても実際の支出とみなされるのは信販会社による一括支払いのタイミングとなるため、全額を申告可能です。
ただし、金利や手数料は控除の対象外となるため注意が必要です。
また、総額の支出がわかるようにデンタルローンの契約書や信販会社の領収書を保存しておきましょう。
家族分を合算できる
同居している・離れて暮らしていても生計を共にしている家族の医療費もまとめて申告できます。全員分の領収書を管理しておくと控除額が大きくなる可能性があります。
【インプラントは基本的に控除対象となるので申請がおすすめ】
インプラント治療は高額になりやすいですが、医療費控除を利用すれば負担を軽くできます。
また、交通費や関連治療費も控除の対象になるため、記録を残しておくと安心です。
インプラントの費用が気になる方は、医療費控除を賢く利用し、経済的な負担を少しでも減らせるよう選択肢のひとつとして考えてみてください。



